 |
 |
 |


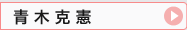
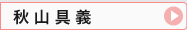
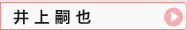
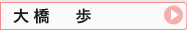
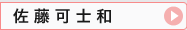
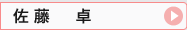
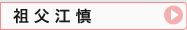
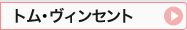
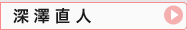

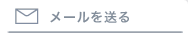
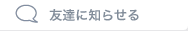


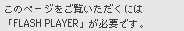 |
 |

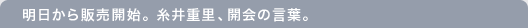
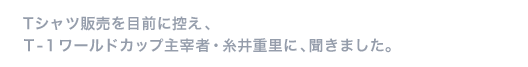
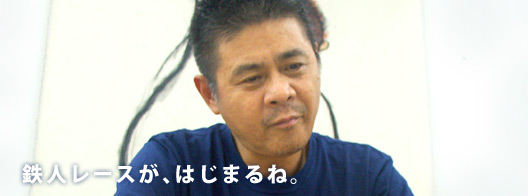

 |
僕が、このT-1ワールドカップを開こうとした
大きなヒントになったのは、
漫才日本一決定戦の「M−1グランプリ」なんです。
お笑いの若い人が、
「M−1があるからこそ一年がある」
と言っていたのを聞いて、
ああ、M−1がなかったら、
出る人たちにとってのあの「場」がなかったんだな、
「時間」が違っていたんだな、と感じました。
デザインや広告の世界には、
そういう「場」は、なかなかありません。
広告のコンペは、与えられた課題にそって
勝つか負けるかしかない、ビジネスです。でも、
「あたらしい剣を編み出したんだけど誰に知らせようか」
「使ってみたい力や道具があるのに、ふるう場所がない」
とデザイナーは考えることがあるかもしれない。
そうことを飲み込める場所をつくりたかったんです。

格闘技のK-1も、考えてみれば、そうですね。
それぞれバラバラのところで闘っていた、
「この人とこの人は、闘うチャンスはないだろう」
と思っていた人たちが、闘える場ができたんです。
今回のT-1出場者のみなさんは、ほんとうに真剣です。
その理由のひとつには、観客の代表として、
ほかの選手がいることがわかっているからです。
別の選手の試合中にリングを見上げている
選手がいるでしょう。
あの状態です。
K-1もM−1も同じですが、
まずは出場者それぞれがものすごい観客だ、ということが
緊張感を生んでいるのです。
自分が誰かと組んでここにいたら、
ヒヤヒヤしただろうなと思います。

ここで、ひとりひとりの選手たちを
もういちど、紹介していきたいと思います。
 |


「畑を一気に耕せ!」と、かけ声を出せる人。
青木さんは、プロデュースとデザインは同じだ、
という考えを持っています。
とてもおもしろい時期にさしかかっているあの人が、
Tシャツが使われる役目とは何か、
何によって価値が出るのか、を考えてくれました。
プロデューサーの青木さんが
デザイナーの青木さんに
「見たことあってもっと広がる可能性があるもの」を
Tシャツに載せて
「このTシャツという畑を一気に耕せ!」
という命令を下したんです。
命令も、走っているのも本人だということが
このTシャツ2枚に、
おもしろいくらいにあらわれている。愉快です。
それに、本人はあまり言いませんでしたけれども、
プリントしにくいことをわざとやっているんですよ。
鉛筆描きのものをプリントしたTシャツなんて、
僕は見たことがない。それに、黒の一色刷りにしたり
線がかすれていたりしていて、隙をつくっています。
これは、福だるまと同じなんです。
「え? 塗っちゃってもいいの?」とか、
「何かいいことがあったら塗ろう」とか、
買った人が思ってくれるくらいに、
そこまで人を巻き込みたいという目を持っているんです。


ひとりのプレゼンターになれる、怖い力を持つ人。
秋山くんの、今回の発言で印象に残っているのが、
「時間を与えられると困る」ということです。
俺に考えさせないでくれ、というプレイを
ものすごく得意としている人です。
脚本を考えないで漫才をする、タレントのようですね。
台本があったうえで練習をする、というのが嫌なんです。
今回、彼がつきぬけたデザインを出したのは、
僕の勝手な想像では、
秋山くんの娘さんの影響があると思うんです。
あのかわいい娘が、「ほちい!」と言ってくれるものを
彼はつくったんです。
それと同時にあの年下の、美人の妻が
「え、わたしもほしい!」と言う声が
彼には聞こえたんだと思います。
そこでは、彼は、アートディレクターというよりも、
プレゼンターになっているんです。
ひとりの「男」になったという、その捨て身の精神が、
秋山具義という人の、怖いところです。
そうなった瞬間に、観客へのプレゼンターにも
当然、なっているわけなんです。
これは、キャアキャア言われるTシャツに
なるでしょうね。


なんでもないものをほんとうにつくろうとする人。
井上嗣也さんのいちばんすごみのある発言は、
「Tシャツというものはさ、どれがいいのか
さがしてくるものなんだよ」
なんです。Tシャツの山のなかにまぎれている状態で
選ばれるようなものをつくろうと思っているんですよ。
これは、長年生きてきた男の発言だなぁ、と思います。
古着屋さんに、くしゃくしゃにして紛れ込ませて、
「ほれ、売れたでしょ。俺でも買うもんな」
と、彼は言いたいのです。
ひねくれているけれども、おもしろいストライクを
ズドーンとねじ込んでいますよ。
彼は「うますぎるんだよな」ということを落とす作業に
ものすごく長い時間をかけていました。
色といい、プリントの技法といい、
何も考えていないフリが「ほんとうに」できるまで、
練り込んでいったわけです。
デザインよりもチョイスこそがTシャツであり、
チョイスをされるなんでもないものを
石ころをつくるように、つくる。
年が近いせいか、嗣也の考えには
共感するところがあります。
「嗣也は、そこに来ているんだな」というのを
ズンズン感じます。


すべてが消えた先にある場所で答えを出した人。
大橋さんは、自分が「着る側のおしゃれさん」として、
いろんなものを見てきた人です。
「これを着ようかしら、と思えるものが
どっかから降ってくればいいのに!」
と思っていて、
「あれば買っちゃう」とみんなが思うようなものを
どうやったらつくれるんだろう、と考えているんです。
自分の個性でビジネスをしながらも、
「個性さえも消えた価値があるもの」を求めている。
このあたりは井上嗣也さんにも
共通していることなのですが、
大橋さんは、プリント部分には何を載せてもいいんです。
「なぜそうか?」ということを抜きにして
「このTシャツがなんだかわからないけど、いい!」
と、飛びつくようにやってくる人がいることを、
どこかで知っているんです。
それに、大橋さんが和のテイストを出してきたところも、
大きなポイントです。こんなにサラッとした和柄は、
僕はあまり見たことがないです。
実はすごく絶妙で、恐れ入りますよ。
大橋さんの、あのかわいいクマや犬をプリントしても
絶対によかったと思うんです。でも、
「いま私がやるべきはそうじゃなくて」と思われたし、
試合だったからこそ、この柄が出てきたんですね。


最後に残った言葉を選んだ、頬の温度の高い人。
可士和さんは、いま、メディアについてずっと考えていて、
建物も人間も看板もテレビもメディアだし、
相互にメディアとメディアが反射し合って
世界ができているととらえているんだと思います。
そして、世界のすべてがメディアになったときに残る
核になるメッセージは何か、といえば、
「PEACE」なんですよ。
今回、この「PEACE」という言葉を敢えて出した、と、
アシスタントの方のインタビューに載っていましたが、
ひと言だけ書くとすれば何だろう、ということになると、
これだったんですね。
「出してもいいのかもしれない」と考えて、
とっておきのものを出してきたという、
ちょっと頬の温度が高いかんじがある、
それがこのTシャツの魅力だと思うんです。
クールにつくっているのに、冷たくないんです。
「PEACE」と言ってみたい気持ち、みんなにも
あるでしょう?
この人は、やっぱりそのあたりがとてもうまいですよ。
それに、ほつれてからどう変化していくか、
Tシャツを着たおしている人のことを
とてもよく考えていると思います。


別荘でゴロゴロ転げ回ることを、さがし抜いた人。
このTシャツは、卓さんの別荘です。
八ヶ岳か奈良かハワイかわかりませんが、
もうひとりの佐藤卓さんの遊び場として
どのくらい「遊び場です」と言えるかどうかを
自分でさがし抜いたんです。
その答えを「そうだ!」と見つけて、
泥んこ遊びをしてる。
制作のようすがビデオに収められていて、
あれを見るとよくわかるのですが、
卓さんのやったことは、まさに「Let's play」です。
「Let's play」がきれいになってしまうということが
卓さんの、すばらしい体癖です(笑)。
そして、泥んこ遊びがひとつではすまなくて、
ちゃんとふたつつくっているというのが
卓さんの底力です。
ほんとに、このTシャツを見ると、わかります。
ゴ〜ロゴロ転げ回っていますよ、
あの「佐藤卓さん」が! たのしいです。
このTシャツは、働き盛りの男性や
キャリアウーマンに、
泥遊びをするように、着てほしい。


人を揺さぶることを知っている人。
祖父江慎さんは、ほんとうにおもしろい人です。
Tシャツのことを話す前に、
ついつい祖父江さんについて語ってしまうのは、
このTシャツが出てくるまでには、
祖父江さんという「人」がいなければならないからです。
T-1に並んだTシャツはどれも、
決して会議の話し合いでは出てこないTシャツですが、
最も会議で出てこないタイプが、
祖父江さんのTシャツなんです。
祖父江さんの発想には、他人の考えでは至れないんです。
つまり、極私(きょくわたくし)。
極私は、誰にでも通じて、そして、人を揺さぶる。
アカハライモリの、あの小さい面積のおなかのなかに、
耳の奥に三半規管がひそんでいると知ったときに、
祖父江さんは、神さまがつくった
「うわぁ!!」というものを発見したんです。
それを僕がやってあげましょ、そして、
「わぁっ!」と言い合いましょ、ということなんです。
デザインやプリントの仕上げには
ふだんどおりに技術を駆使しているのですが、
いちばんこまかい計算をしていそうなこの人が、
いちばんの芸術家だったのかもしれませんね。
雨を凌いで練習をしているダンサーのような心を
持つ人たちに、このTシャツを着てほしい。
鏡に映る自分を見て「うわぁ!!」と思ってほしいな。


「ここからはじまる世界」をTシャツに託した人。
トム・ヴィンセントさんのつくったTシャツは、
まさに、絵本です。一枚の絵本を2冊つくったんです。
曲のラインで詞を考えてもらう作曲家と同じで、
ここに載せる物語は、あなたがどんどん考えてください、
と、共作を要求するTシャツです。
そんな絵本作家が、Tシャツ上では存在できるんですね。
トムさんのTシャツを着てみんなが集まったら、
その部屋のなかは物語でいっぱいになる。
そういうおもしろいことが、ほんとうに楽しく
このTシャツでは、できるんです。
プリント部分には、雨が降っている絵が載っています。
「なぜ雨が降ったの?」「お母さんが思うにはね‥‥」と、
Tシャツが転がっていくことで物語が生まれます。
トムさんは、そういう遊びをしたかったんです。
イギリスからやってきたトムさんが、
静かな夜中に、誰かとこうやって話をしているんだろうな、
もっと通じる何かを、
どうにかして見つけているんだろうな、と僕は推測します。
着たときに「それは‥‥」と、
ちょっとだまって見てもらっているときに、
ふたりのあいだそのものをたのしめるメディアを、
トムさんは、考えついたんでしょうね。
横のラインのところは、本の帯に近い感覚だと思います。


あらゆることをきちんと追い込んだ、勝負の人。
深澤直人さんは、特に、工業デザインをしていますから、
ふだんは、多くの人と関わり合いながら仕事をしています。
深澤さんのTシャツは、たったひとりで、
音に耳をすますようなデザインです。
ふだんそういうお仕事をなさっているからこそ、
こういうものが生まれたのだろうなと思います。
ここに至るまでの作品も何点か拝見しましたけれども、
ポーンと一音だけ叩いた音を
ここまできれいに表現できるのは、
そうとうな技量、そして、度胸が要ることです。
それに、深澤さんは、試す作業を何回もやっています。
「コンセプトができたから、できた」ではなくて、
これじゃだめだ、これだといい、人に着せてみる、
そんなことをさんざんやって、
「これならみんながちゃんとわかってくれるだろう」
というところまで追い込んでいます。
こういう種類の仕事は、追い込めなかったら
それでおしまいなんです。
深澤さんは、いちばんの勝負に出ている人ですが、
ルーレットでいうと、一見、
36個の数字のひとつに賭けているようにも見えます。
でも、はずれる勝負をするつもりは全くないんですよ。
この人は、ずいぶん男らしい人だ、と僕は思いました。
このT-1ワールドカップは、お祭りです。
運動会にも「赤勝て、白勝て」があるように
「Tシャツ」というもので勝敗をワイワイ騒ぐ。
こういうことを、ほんとうに僕は、
ずっと、やってみたかったんです。
T-1は、今回が、第1回です。
きっと、まだまだ枝葉もつくだろうし
もしかしたら幹そのものも
変わっていくかもしれないけれども、
どんなことになろうとも、真の意味で
「ワールドカップ」にしていきたいです。
いまはまだ、よちよち歩きだけどがんばれ、
という気持ちです。
これからは、ちょっとおおげさにいうと
ソフトが財産になる時代です。
それぞれの国がアイデアやデザインで
切磋琢磨していく時代に入ります。
この、日出ずる国から
逆光で9人が登場してね、
世界に問いかけるわけですよ。

記念すべき第1回に出てくれた
9人の選手たちは、
自分のTシャツがもし勝ったら
そうとううれしいだろうと思います。
うきうきしたかんじで喜んでくれるでしょう。
それが、いまからわかります。
それに、僕はいまから、わくわくします。
みなさん、どのTシャツを選ぶか、
決まりましたか。
明日から、販売は開始です。
|
 |

 |
2005-10-04 |

|

 |
 |
|
 |


|
 |
 |